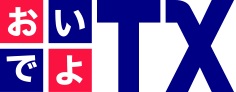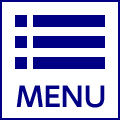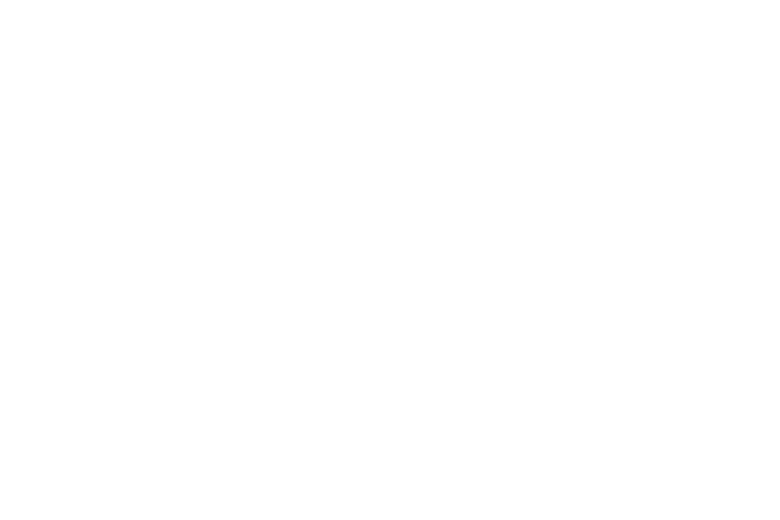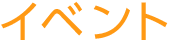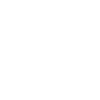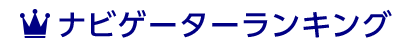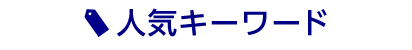子どもも大人も凸凹(違い)を認め合える社会を目指して活動をしている、特定非営利活動法人オトナノセナカは、年に一度「6歳までに知っておきたい!素敵な幼児教育コレクション」と題した子育て手法セミナーを実施。さまざまな幼児教育法を知ってもらうことで、意思を持って子どもの教育法を選択してほしいという思いが込められています。セミナーでは“対話”の時間をたっぷりと設けているそうです。
7/19(日)・20(月・祝)に柏の葉キャンパスで開催された「マナビーヤ!フェスタ」で、その一部が体験できるワークショップが行われ、その“対話”のポイントについて紹介されました。

オトナノセナカ代表理事の小竹めぐみさん
対話に必要な5つのポイント
では対話の実践ポイントを5つご紹介します。
1.聴く
ついついやってしまいがちですが、相手の話を遮らないようにしましょう。分かった気になって相手の話を止めてしまったり、自分の話を始めたりすることがあるかもしれません。最後まで聴ききること。これが大事です。
2.伝える
うまくまとまっていなくてもいいので、自分の言葉で伝えましょう。「私も一緒でいいよ」とか、「同じ」と言うのはすごく簡単ですが、自分の言葉で伝えることが大事です。

3.違う意見
ご夫婦や保育士さんと意見が違ってしまうこともあるかもしれません。それをチャンスととらえましょう。違う意見を持っている人からは、たくさん学べることがあります。「そうじゃなくて」なんていう否定の言葉を使ってしまうと相手も悲しくなってしまいますね。「なるほど、そうだよね。でも私はこう思ってるよ」という形で、相手も自分も大事にするような聴き方、話し方にしてみてください。
4.もやもや
もやもやすることに気づけたら、そんな自分に拍手をしましょう。ちょっと気になるけどいいや、なんてうやむやにしていることはないでしょうか。もやもやは、今よりもっとよくなれるチャンスです。もやもやに注目を。
5.沈黙
しーんとなる時間も実は大事な対話の時間です。来るべきときに来るものなので、心配しなくて大丈夫です。
そして最後にもうひとつ、時に脱線することも大事です。
“対話”は、なんとなく話す“会話”とは違います。対話は考え方を知り合うことです。勝ち負けを争う議論ではないので、相手に勝とうとしなくていいのです。知り合うための対話ならけんかする必要もないですよね。“対話”は、多様性と自分らしさに出会うことのできる時間。夫婦の間でも、子どもとの間でも、友達との間でも、日常生活の中でぜひ意識してみてください。

親子連れでにぎわうイベント会場